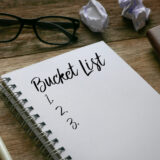「お彼岸」は、仏教と非常に深い関わりがあるものです。
今回はこの「お彼岸」を取り上げて、その基礎知識やお彼岸で行うこと、お彼岸のお供え物とそのマナーについて解説していきます。
2025年のお彼岸と、お彼岸の由来
お彼岸の「彼岸」は「岸の向こう側」「あの世」「悟り」「煩悩から開放された人が行きつくところ」:という意味を持ちます(なお「この世」を意味する言葉は「此岸・しがん」です。元々はサンスクリット語の「パーラミター」という言葉から来ていて、これを「到彼岸(とうひがん)」と呼んだことから、この名前が付けられました。
お彼岸は、その名前からも想像できる通り、仏教を土台としている言葉・風習です。ただしこのお彼岸は、仏教の生まれ故郷であるインド仏教にはない風習であり、日本の仏教独自の考え方です。
さてこのお彼岸には、「秋のお彼岸」と「春のお彼岸」の2つがあります。
秋のお彼岸は秋分の日を真ん中に挟んだ前後3日間、春のお彼岸は春分の日を真ん中に挟んだ前後3日間です。秋のお彼岸も春のお彼岸も、年によって微妙にその日付が代わることがありますが、2025年の秋のお彼岸は9月20日~9月26日、春のお彼岸は3月17日~3月23日です。秋分の日と春分の日は、昼と夜の長さが同じであることなどから、「あの世とこの世がもっとも近づく日である」と考えられ、「お彼岸」とされるようになりました。
お彼岸では何をする?
お彼岸は、自分の身を慎み、先祖に思いを馳せる日だとされています。
行うことは、主に下記の4つです。
- 仏壇のお参り
- お墓参りと墓掃除
- お寺での彼岸法要に参加する
- 個別に彼岸法要を行う
基本的に、番号が若い項目の方が一般的で取り組みやすく、行っているご家庭が多いものです。
一つずつ解説していきましょう。
仏壇のお参り
まず、家にある仏壇にお参りします。
仏壇を開き、お供えをしましょう。なおお供えに関しては、「普段通りのものでよい」としているところもある一方で、「いつもより贅沢なものをお供えする」と考えるところもあります。このあたりはご家庭ごとに決めても構わないでしょう。
仏壇の掃除もこのときに行います。基本的にはからぶきでかまいません。洗剤などを使う場合は、専用の洗剤を使います。専用の洗剤がない場合は、水で薄めた中性洗剤を使いましょう。
※お供え物の詳細については次の項目で詳しく解説します。
お墓参りと墓掃除
お彼岸にお墓参りを行うご家庭は、非常に多いものです。また、お墓参りを行うときに、一緒にお墓の掃除も行いましょう。
濡れた雑巾などで水ぶきをするのが基本になりますが、文字部分などが汚れているのであれば歯ブラシなどを使って汚れを落とします。花立や線香台も、しっかり水ぶきをしてほこりをとりましょう。花立や線香代はお墓そのものよりも汚れがたまりやすい傾向にあります。
洗剤は、汚れがひどくない場合であれば使う必要はありません。使う場合はこれも専用の洗剤を使いますが、墓石業者などにお手入れ方法を聞いておくとより安心です。
掃除の過程で、ひびわれやカケなどが見つかった場合は、自分たちで対応しようとはせず、必ず墓石業者に連絡をしてください。
お墓掃除は、ご家族皆さんで行われるのが理想的です。掃除が終わったらお供えをして、しっかり手を合わせましょう。
お寺での彼岸法要に参加する
お寺では、お彼岸の時期に法要を行っています。「施餓鬼(せがき)法要」などがそれで、これに参加することもできます。「合同供養」とも呼ばれるもので、個別での法要に比べて酸化しやすいのが魅力です。「事前の予約は不要」としているところもあるので、菩提寺の法要スケジュールを確認しておくとよいでしょう。
なおお寺での彼岸法要には、3000円~10000円ほどのお布施を包んでいくとよいとされています。ただしお布施に関しては、事前に「5000円」などのように明確な数字を出しているお寺もあるので確認しておくとよいでしょう。
個別に彼岸法要を行う
現在では少なくなりましたが、個別に彼岸法要を行うご家庭もないわけではありません。この場合は、「お寺に赴いて法要に参列する」というかたちではなく、「ご僧侶に、自宅やお墓に来てもらって法要を執り行ってもらう」というかたちになるでしょう。
相当に信心深いご家庭であったり、故人のご意向であったりする場合はこの個別の彼岸法要を行うのもよいものですが、この場合のお布施は合同法要に参加する場合よりも高額になります。一般的には、30000円~50000円、さらにお車代が必要です(※お寺から徒歩圏内あるいは呼ぶ側が送り迎えをする場合は除く)。
お彼岸でお供えするもの、そのマナーや選び方
ここまで、お彼岸の基本的な意味や、お彼岸に行うことについて紹介してきました。
最後のこの項目では、「お彼岸にお供えするもの」のマナーと選び方について取り上げていきます。
ここで取り上げるのは
- 和菓子類
- お花
- 果物などのお供え
- ろうそく
- お香
ですが、このお供え物に「優先順位」はありません。5つすべてをお供えすることもできます。
おはぎ?ぼたもち?お彼岸団子とは
お彼岸には、おはぎやぼたもち、お彼岸団子といった和菓子類をお供えします。
おはぎとぼたもちは、もち米とあんこを使って作るお菓子です。おはぎは秋のお彼岸のときに作るもので、粒あんを使って作ることが多いものです。対してぼたもちは春のお彼岸のときに作るもので、こしあんを使って作るのが一般的です。なお「おはぎ」は「萩」を、ぼたもちは「牡丹」を名前の由来としているとされています。
※作り方や呼び方については諸説あります。
「お彼岸団子」は、丸く丸めたお団子のことをいいます。月見団子に似た形をしていることが多いのですが、それを平べったく整えた「彼岸餅」と呼ばれるものもあります。地域によって呼び方が異なりますが、ご家庭によっては用いないこともあります。
お花の選び方
仏壇やお墓にお供えする花は、菊に代表される仏花が基本です。ただしお彼岸のお供えのお花のルールはそれほど厳格なものではないため、季節のお花をお供えしたり、故人が愛したお花をお供えしたりと、柔軟な考え方をしてもかまわないでしょう。
基本的には
- 棘のある花
- 香りが強すぎる花
- 花粉が落ちる花
などは避けるべきとされていますが、故人の強い希望があったのなら、これらも許容されます。
果物などの食べ物は「持ち帰り」が原則
お彼岸では、お墓に果物などの食べ物をお供えする人も多いことでしょう。しかしこれには注意が必要です。
なぜなら現在は、お墓にお供えした食べ物は「その場で持ち帰ること」が基本となっているからです。
鳥や虫による被害や腐敗を避けるために、食べ物は「お墓にお参りするときに持っていって、お供えをして、持って帰ること」が基本となります。
なお持って帰ったものはそのまま「おさがり」として頂くのが基本です。
現在はろうそくも多種多様
「果物などをお供えしても、持って帰らなければならないのはいかにも寂しい」「故人とともに好物を味わいたい」という人におすすめなのが、「食べ物型のろうそく」です。
現在はろうそくも多種多様で、ビールやお寿司、果物やお菓子などをかたどったろうそくが数多くリリースされています。しかもこれらは非常に精巧にできています。お供えの食べ物の代わりにこれらを持っていく(あるいは食べ物にプラスして持っていく)ということもできますから、利用するとよいでしょう。
もちろん、一般的なろうそくを持っていってもかまいません。
お香、どんな香りを選ぶ?
お香は故人を非常に喜ばせるものです。
基本的には仏前用のお線香などでかまいませんが、お彼岸のシーズンには、少し香りにこだわったものを選んでもよいでしょう。
故人が愛した香りがあるのであればそれを選ぶのがもっとも理想的ですが、それ以外にもさまざまな香りがあります。またなかには、ろうそくとお香がセットになったものもあります。
お香の香りは多種多様です。実際にかいでみて、自分好みのものを選ぶのがよいでしょう。
ご先祖様に思いを馳せる「お彼岸」は、特別なものです。心静かに、「その日」に向かい合いましょう。
贈儀計画コラムでは、人生の儀式における皆さまの悩みをサポート致します。
葬儀・介護・相続・お墓・結婚などそれぞれの課題を、情勢に合わせ専門のサポートスタッフがいつでもご相談を承ります。まずはお気軽にご相談ください。
冠婚葬祭セリエンス(贈儀計画コラム運営企業)
電話番号:0120-34-5183 受付時間:9:00-17:00
インターネットでのお問い合わせは24時間承っております。